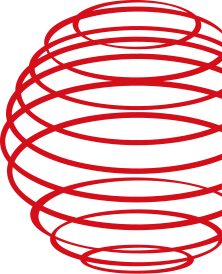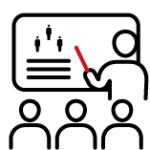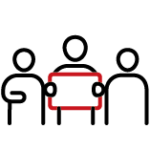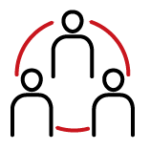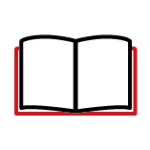シティズンシップ教育研究大会2025(二次案内)
日本シティズンシップ教育フォーラムでは「研究」に力点を置いた交流と研究発展に向けた場として、9月28日(日)に「シティズンシップ教育研究大会2025」を開催いたします。
「シティズンシップ教育研究大会」は、「シティズンシップ教育」をキーワードに、多様なディシプリンの垣根を越えた知見交流を通じて、これまでの自らの研究のあり方を振り返り、今後のシティズンシップ教育研究のありようを共に考えるプラットフォームとして、2019年度から開催してまいりました。これまでの研究大会では、政治学・社会学・教育学・心理学・哲学など多様なバックグランドの研究者はもちろんのこと、実践者、大学院生、学部生などの参加もありました。
今年度も、多様な研究者、学生のみなさんを繋ぐ場となればと考えています。本大会はオンライン開催となっています。オンラインであることのメリットを生かし、地理的に離れた場所にある方々を繋ぐ契機になればと考えています。
今回のシンポジウムのテーマは、「現代のシティズンシップ教育の見取図を考える」です。多彩な研究/実践が広がるシティズンシップ教育の全体像を捉える見取り図を手にすることは、私たちが垣根を越えた知見交流を進めたり、共同研究/協働実践を進めたりする上で重要なことでしょう。そこで、日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)が監修し、今夏に公刊されるテキストを議論の起点に今回は置き、その到達点と課題点を見つめながら、どのような見取り図を私たちは創り出していくべきかを考えていきます。
この分野の研究に長く取り組まれてきた方々のみならず、大学院生や学部生の方を含む若手の方や、新たに関心を持たれた方、さらに他分野へのつながりをつくりだしたい方にもぜひ積極的にお越しいただき、今年度もシティズンシップ教育研究をともに切り拓いていくプラットフォームとなれば幸いです。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
1.概要
■日時:2025年9月28日(日)10時〜17時30分(任意参加のアフタートークは18時30分まで)
■会場:オンライン開催(参加者の方々にzoomミーティングルームのURLを共有します)
■対象:シティズンシップ教育研究に関心をもつ方々なら,誰も参加できます。
若手研究者・院生・学部生の参加を歓迎いたします。
■主催:日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)
2.全体スケジュール
10:00~12:00 シンポジウム「 現代のシティズンシップ教育の見取図を考える」
13:15~15:00 自由研究発表セッション(1)(分科会ごとでの実施)
15:30~17:15 自由研究発表セッション(2)(分科会ごとでの実施)
17:30〜18:30 アフタートーク(任意参加)17:30〜18:30 アフタートーク(任意参加)
3.参加費
・高校生:無料
・学生・院生:500円(発表者:無料)
・一般:1,000円
4.研究大会への参加方法
加者登録をした方に,シンポジウム・自由研究発表の zoom ミーティングルームにアクセスするための情報 を事前にメールでお知らせいたします。参加を希望される方は以下のアドレス( https://cerc2025.peatix.com )よりお申し込みください。
5.大会企画
今回の研究大会では、二種類のセッションで企画を構成します。
(1)シンポジウム
参加者が一同に会し、共にシティズンシップ教育研究について考えます。
(2)自由研究発表セッション
発表者の研究成果について口頭で発表し、参加者と質疑応答やディスカッションを行います。
(1)シンポジウム
■テーマ:現代のシティズンシップ教育の見取図を考える
■趣旨:
日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)は2023年に設立10周年を迎えた際、記念事業として出版企画を勧めるプロジェクトを立ち上げました。そのねらいは専門分化していく研究/実践を横断的につないでいくための見取り図の一つを提起することでした。
2002年のイングランドでのシティズンシップ教育の制度化の動きを受けて、日本でもシティズンシップ教育に対する関心が集まるようになりました。そこから20年余を経た現在、シティズンシップ教育研究には広がりと深まりが見られるようになりました。毎年、厚みのある研究成果が出版/発表され、本研究大会でも各分野から数多くの研究報告がなされるようになっています。
こうした広がりと深まりの進展によって、全体像をつかみ取る難しさが増しているようにも思われます。特に初学者にとってはなおさらでしょう。そこで全体像を捉えるための見晴らしを良くする入門書を出版することになりました。こうした企画を進める際、各方面でどのような研究/実践の蓄積がなされているのかを把握するのみならず、「これまで」のシティズンシップ教育の見取図で十分な扱いを受けていなかったことが何か、「これから」のシティズンシップ教育で重視して扱うべきことが何かといった問いに対して、現代的視点からの再考が求められることになります。
その結果を踏まえて、28名の方々に筆を執っていただいた『民主的社会をつくるシティズンシップ教育』がナカニシヤ出版から今夏に公刊されます。本シンポジウムでは、同書の試みを参照点の一つとしつつ、現代のシティズンシップ教育の見取り図とはどのようなものか、皆さんと一緒に考えていきます。
■登壇者
川口広美さん(広島大学大学院人間社会科学研究科准教授)
桑原敏典さん(岡山大学学術研究院教育学域教授)
郡司日奈乃さん(千葉大学大学院人文公共学府博士後期課程)
杉浦真理さん(立命館宇治高等学校継続雇用教諭, 大阪大学非常勤講師)
杉浦真理さん(立命館宇治高等学校継続雇用教諭, 大阪大学非常勤講師)
古田雄一さん(筑波大学人間系助教)
古野香織さん(認定NPO法人カタリバみんなのルールメイキング課題解決ユニットリーダー)
■コーディネーター
斉藤仁一朗さん(東海大学資格教育センター准教授)
(2)自由研究発表セッション
自由研究発表は分科会(1発表につき持ち時間35分(発表時間15分~20分、質疑応答15分~20分)の開催を予定しています。
*研究大会としての性質に鑑みて、次のような発表を想定しています。
(1) 研究成果を発表し、フィードバックを得る(通常の学会発表と同様)(2) 構想段階や計画段階にある研究を発表し、研究を進めるためのフィードバックを得る
(3) 他の学会等で既に発表したものを再び発表し、異なる視点からのフィードバックを得る
(卒論のプレ発表/修論のプレ発表、および学会未経験者の発表でもよい)
−自由研究発表プログラム−(発表要旨は https://jcef.jp/project/cerc/cerc25abstracts.html をご覧ください)
<第1ラウンド(13:15~15:00)>
[第 1-1 分科会]
司 会:若槻 健(関西大学)
副司会:原田亜紀子(東海大学)
(1)生徒参加実践における「生徒の声」の位置づけに関する研究
―X高校三者協議会を事例として―
小澤莞介(筑波大学大学院)
(2)スウェーデンにおける外国生まれの若者の市民活動への参加に関する一考察
―若者同士や職員の関係性に着目して―
葉上千紘(大阪大学大学院)
(3)学校における校則見直しの進捗に影響を与える要因
―生徒の意見表明・意見反映との関連に着目して―
阿竹隼耶(認定NPO法人カタリバ)
古野香織(認定NPO法人カタリバ)
古田雄一(筑波大学)
[第1-2分科会]
司 会:市川享子さん(東海大学)
副司会:川中大輔さん(関西学院大学)
(1)市民アドボカシーによる「災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第217回国会閣法第17号)の成立」
―専門知による政治参加促進の教育への反映―
宮﨑一徳(みんなの政策研究所)
(2)学生団体を「小さな公共」として位置づけた伴走支援
―プロセスコンサルテーションの視点から―
白川陽一(名城大学社会連携センター)
(3)地域福祉実践における福祉教育の価値を再考する
―ライツ・ベース・アプローチによる実践について―
西村洋己(兵庫県立大学大学院・岡山県社会福祉協議会)
[第1-3分科会]
司 会:北山夕華さん(大阪大学)
副司会:久保美奈さん(千葉経済大学)
(1)外国にルーツを持つ子どもに対するグローバル・シティズンシップ教育の方法に関する研究の構想
―韓国の小学校における実践を手がかりにして―
小西裕美(岡山大学大学院)
(2)外国につながる青少年等の支援団体の管理職の認識に関する探索的検討
―アメリカ合衆国の支援団体を事例として―
坂口(山田)有芸(摂南大学)
(3)言語的文化的に多様な子どもの社会との接続を図る教師の行為
―民主的文化のためのコンピテンシー参照枠を手がかりに―
細野花莉(広島大学大学院)
[第1-4分科会]
司 会:岩崎圭祐さん(鹿児島大学)
副司会:橋崎頼子さん(奈良教育大学)
(1)少年院における法務教官の教育観に関する研究
―法務教官の生活史に着目して―
橋本幸弥(岡山大学大学院)
(2)シティズンシップを支える教師のポジショナリティ
―小学校における実践事例を通して―
大熊英敬(元・東京学芸大学教職大学院)
(3)イタリアの中等教育におけるシティズンシップ教育の目標に関する研究の構想
―教師に対するアンケート調査を手段として―
チョウ・バイ(岡山大学大学院)
[第1-5分科会]
司 会:小栗優貴さん(京都教育大学)
副司会:井上昌善さん(愛媛大学)
(1)Scratchによる主権者教育ゲームの試作
内田保雄・小野創太・雜賀智子(宮崎産業経営大学)
藤本将人・坂本眞人・小林博典(宮崎大学)
(2)絵本を活用した幼児の市民性育成に関する研究
―親子を対象とした読み聞かせ会の実践を通して―
JIN CHEN (岡山大学大学院)
(3)フィールドワークは高校生の人権意識にどのような変化をもたらすか
―国立ハンセン病資料館の見学から―
水野雄人(東京都立東久留米総合高等学校)
<第2ラウンド(15:30~17:00)>
[第2-1分科会]
司 会:井上昌善さん(愛媛大学)
副司会:小野創太さん(宮崎産業経営大学)
(1)言語学から考える歴史教育研究
―シティズンシップ教育を目指して―
丸小野壮太(常磐大学高等学校)
榮谷温子(慶應義塾大学)
(2)中学校社会科地理的分野におけるサービスラーニングの視点からの単元開発
―世界地理 アフリカ州の授業実践を例にして―
村木龍太郎(東京学芸大学附属世田谷中学校)
(3)北海道の子どもたちはナショナルヒストリーをどう意味づけているのか
―小学生と中学生の歴史的意義(Historical Significance)の比較分析―
澤野友甫(北海道教育大学札幌校・学生)
[第2-2分科会]
司 会:橋崎頼子さん(奈良教育大学)
副司会:市川享子さん(東海大学)
(1)音楽科における市民性育成を目指した異文化理解教育のあり方に関する研究の構想
―伝統音楽を取り上げた授業開発を通して―
小西光(岡山大学大学院)
(2)地域における過去の記憶継承に着目した教材・授業開発
―江別市のアイヌ学習に着目して―
深見瑛導(北海道教育大学札幌校・学生)
[第2-3分科会]
司 会:北山夕華さん(大阪大学)
副司会:星 瑞希さん(北海道教育大学)
(1)遠い戦争と身近な暴力を結びつける国語科平和教育の研究
―戦争を自らの生活と連続する問題として捉える学習者の思考過程の分析―
樋口航生(立命館大学大学院)
(2)「困難な歴史」を読み物としてどう教材化したのか
―小池喜孝の『北海道の夜明け』と『常紋トンネル』を比較して―
三浦幹生(北海道教育大学札幌校・学生)
(3)Examining Patriotism Education in Social Studies: Views of Japanese Junior High School Social Studies Teachers on Patriotism
Okota-Wilson Nicholas (Okayama University)
[第2-4分科会]
司 会:川口広美さん(広島大学)
副司会:別木萌果さん(都立小川高等学校)
(1)恋愛が分からないのは異常か?
―恋愛感情や性的惹かれを前提とした社会規範に抗う教育実践に向けて―
末原幸統(鳴門教育大学大学院)
(2)証言的対話に基づいたアライの教育プログラムの開発
入澤充(東京大学大学院)
(3)小学校社会科の「我が国の歴史」における教科書記述は、どのような男性像・女性像を描いているのか
黒蕨優斗(北海道教育大学札幌校・学生)
[第2-5分科会]
司 会:久保美奈さん(千葉経済大学)
副司会:若槻 健さん(関西大学)
(1) 教育における形成的正義
―校則改正における正義の学習と教育―
小林勇樹(独立研究者)
(2)こども大綱策定・推進にみる子どもの権利保障に向けた可能性と課題
鈴木草営駒(名古屋大学大学院)
(3)アイヌに対するステレオタイプから脱却し、マジョリティの特権性を理解する授業開発
―今を生きるアイヌの多様性に着目して―
水上嘉斗(北海道教育大学札幌校・学生)
[第2-6分科会]
司 会:古田雄一さん(筑波大学)
副司会:樋口大夢さん(東洋学園大学)
(1)日本の教育政策における「新自由主義」の展開過程
―臨時教育審議会の政策動向を手掛かりに―
近藤真鈴(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)
(2)H・アーレントの政治思想とその実践的展開に関する研究
―アーロン・シュッツ(Aaron Schutz)の理論と実践に着目して―
深谷周平(広島大学大学院・学生)
(3)社会科教育学研究における歴史と政策の結びつき
―内海巖による社会科成立期の学習指導要領に関する研究の場合―
釜本健司(新潟大学)
<アフタートーク(任意参加)17:30~18:30>
任意参加のアフタートークを実施します(入退室自由)。
アフタートークでは、テーマ別に話題共有できる複数の部屋を用意いたします(移動自由)。
6.「シティズンシップ教育研究大会2025」実行委員(五十音順)
市川享子(東海大学健康学部准教授)
井上昌善(愛媛大学教育学部准教授)
小栗優貴(京都教育大学社会科学科講師)
川口広美(広島大学大学院人間社会科学研究科准教授)
川中大輔(関西学院大学人間福祉学部専任講師) <委員長>
北山夕華(大阪大学大学院人間科学研究科教授)
久保美奈(千葉経済大学経済学部専任講師)
斉藤仁一朗(東海大学資格教育センター准教授)
橋崎頼子(奈良教育大学教育学部教授)
古田雄一(筑波大学人間系助教)
星 瑞希(北海道教育大学教育学部准教授)
若槻 健(関西大学文学部教授)
7.お問合せ先 日本シティズンシップ教育フォーラム(J-CEF)事務局 E-mail:jcef2013■gmail.com(担当:川中)(■を@に変換してください)